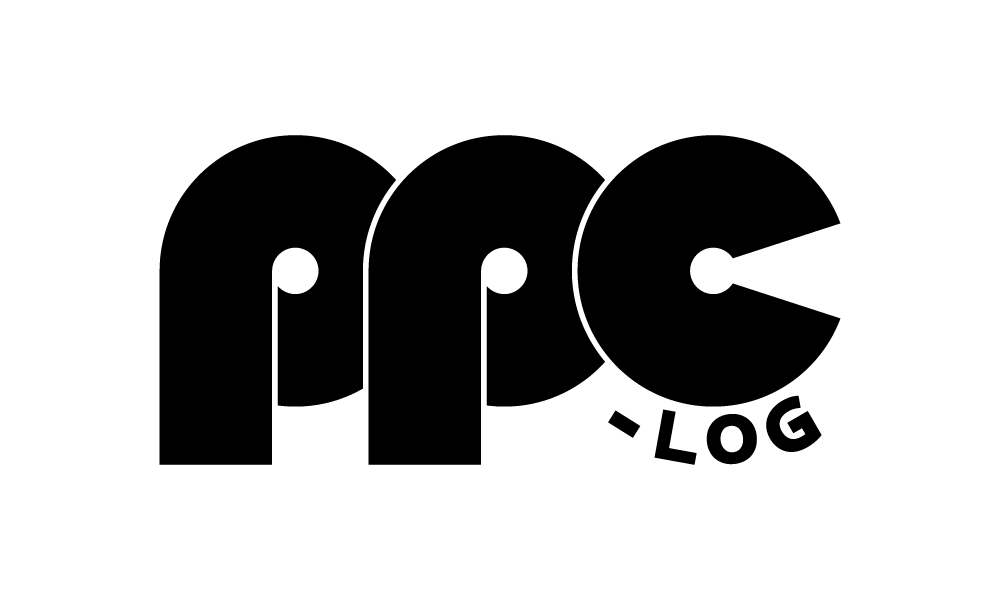当サイトは、Amazon.co.jp の商品を宣伝することにより、紹介料を獲得できる Amazon アソシエイト・プログラムの参加者です。
当記事に Amazon へのリンクが含まれている場合、それをクリックし買い物をすると、当サイト(および当サイト管理人)に対して一定の収益が発生します。
発生した収益の一部は、持続的なサイト維持のために使用されます。
ちなみに下記リンクをクリックし Amazon内で何かしら買い物をしていただくと、当サイト内で紹介した商品以外の購入でも収益は発生します。
もし「ブログの内容が役になった」「記事のおかげで助かった!」といった方は上記リンクをクリック頂き、Amazon内で買い物をしていただければ幸いです。
悩ましいのは、協力頂いた皆さんには持続的なサイト維持以外何の見返りもないということです。せめて皆さんから頂いた額を見て、ブログ読者の方への感謝の気持ちを忘れぬよう日々努めます。
よく社内外の20代の子から「おすすめの本ありませんか?」と聞かれる機会が多々あるので、選書リストを作ってみました。
広告運用者にとっての必読書は「広告運用 書籍」とか検索すればすぐ出てくるかと思います1。
そういった趣旨ではなく、基本的に自分の思想形成や、仕事のやり方に直接強い影響を与えたような、広告運用からは比較的遠い書籍を中心にリストアップしてみました。
今回は9冊リストアップしました。1冊ずつ紹介していきます。
目次
初読は大学3年生の春休みでした。
元々『天才たちの日課』という書籍を読んだ際にアインランドの存在は知り、その中で「ベンゼドリンを欠かさず打ち、慢性的な疲労と戦いながら、あるときは30時間連続で執筆されて出来上がった小説」と紹介されていたため、気になって購入し、春休みを丸々使い、通読しました。
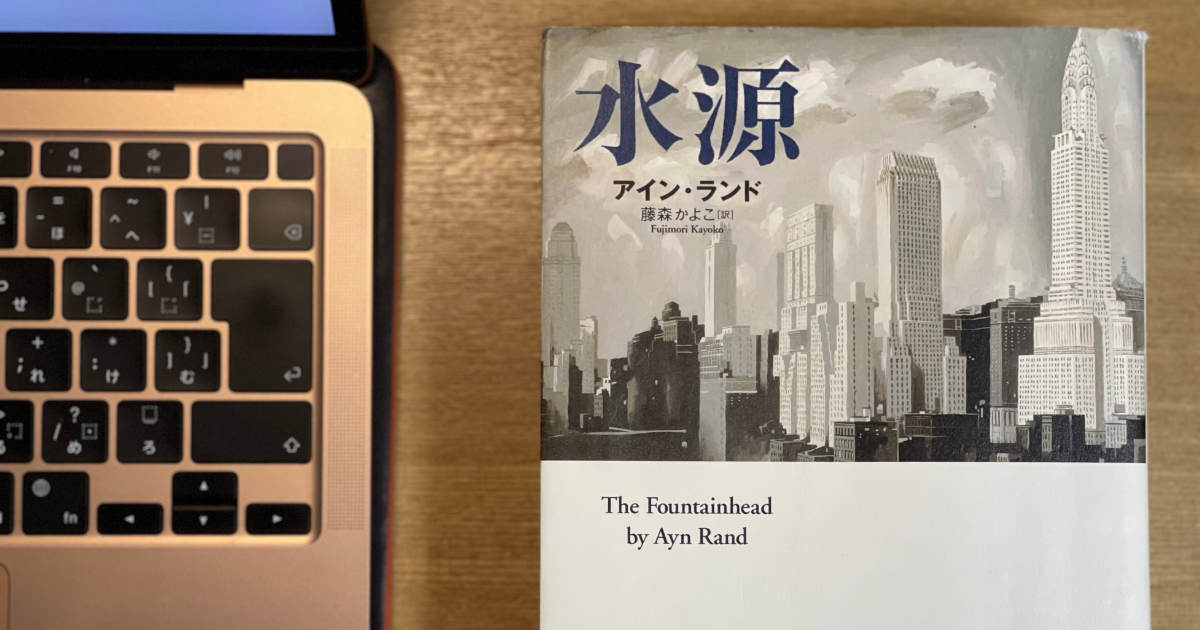
この書籍をきっかけに、自分は存在自体理解していなかったリバタリアン思想について触れ、アメリカのはびこる利己主義な思想性について認識するようになります。
リバタリアン思想について理解していく中で、現在の GAFAM などの出現が如何に必然的なものであったのか、そして自分たちもそれらが生み出した大きな流れの中で、「広告運用」という仕事に携わっているのか、考えさせられるようになりました2。
また主人公の仕事(建築)に対する入れ込み具合に深く共鳴し、「…仕事とはこのように取り組むべきものなのか」と考えさせられた1冊でもあります3。
全編1,000頁超の上下段の構成で通読に時間がかかる作品ですが、長期休暇などを利用して集中的に短時間で読むことをオススメします。
また後に書かれた『肩をすくめるアトラス』もオススメです。
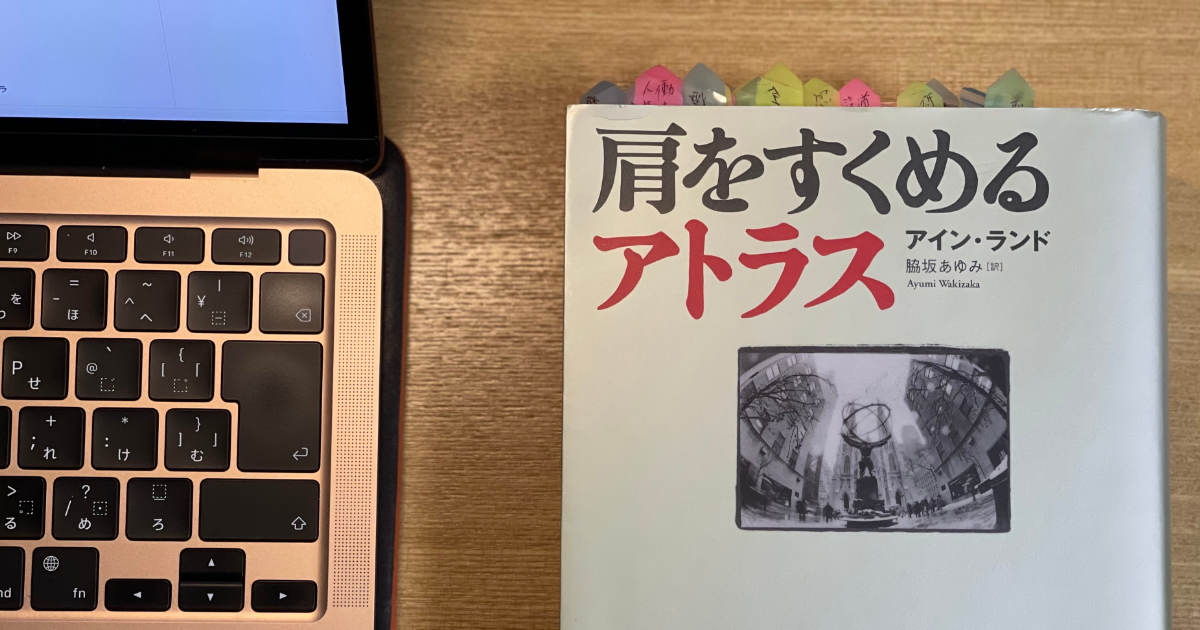
ただ『水源』よりも長編な上、個人的には文章も『水源』の方が読みやすいと思うため、「どちらを読むべきか?」と質問されたら『水源』と答えるようにしています。
『水源』同様、『獄中記』も最初に読んだのは大学3年生の時でした。
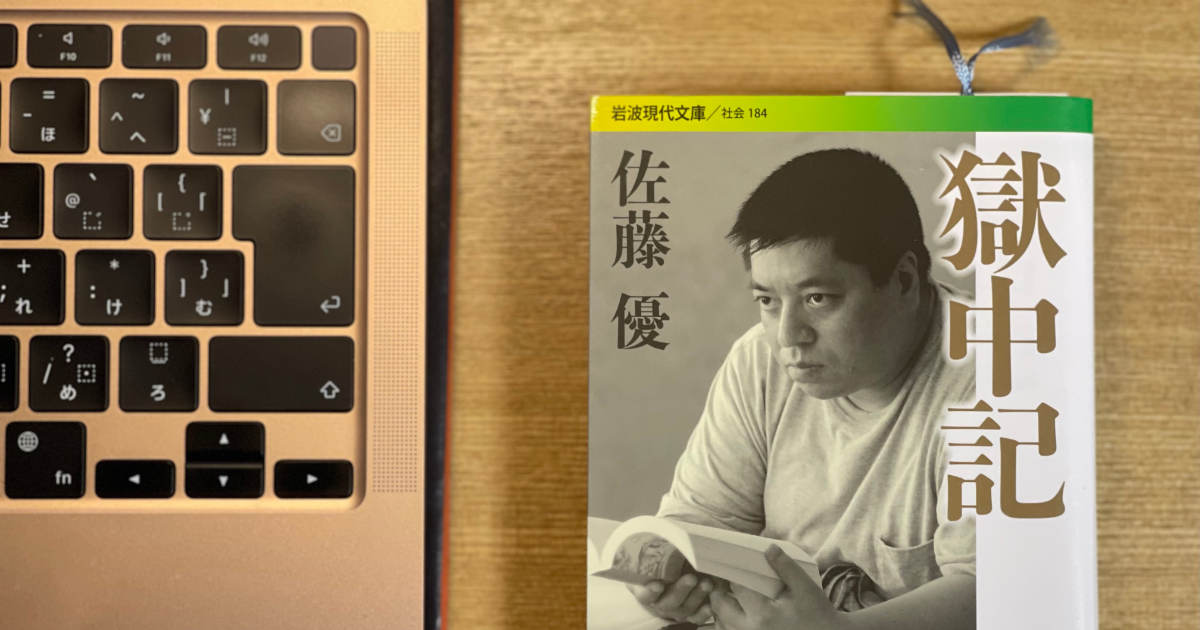
『獄中記』では自身が国策捜査の対象となり、微罪容疑によって逮捕、接見禁止のまま512日間勾留された際の体験を、62冊のノートを頼りに回想し、書かれた書籍になります。
通読することで、氏が如何に512日間の期間を活用し、拘置所内での読書や、思想形成に充てていたのか理解することができます。
佐藤氏の高い記憶力と高度な情景描写力によって書かれる文章は、まるで読んでいるとその場に自分自身がいるのではないか?と錯覚させるほどです。
長く働いていると、辛い仕事や難易度の高い交渉に自分自身が関わらざるを得ないことが多々あります。
ただ幸いにも、自分の場合、仕事上の不運に巻き込まれたり、難易度の高い交渉に失敗したとしても、国益を損なうようなことや東京地検特捜部が令状を持ってオフィスにくるようなことはありません。
再読するたびに、「自分の置かれている状況は佐藤氏のそれと比べまだまだだな…」と冷静に考えるきっかけにもなりますし、これから現状の打開策を探っていこう…と思う際などに、とても役に立ちます。
自分はこの1冊で佐藤氏のドライブ感ある文体に惚れ込み、その後『国家の罠』や『自壊する帝国』、そこから時間を経て書かれた『十五の夏』なども一読するようになるのですが、全てはこの1冊がきっかけでした。
『大河の一滴』などで有名な五木寛之が翻訳を担当し、複数回の改訂版を経て、今なお売れ続けている新潮社のロングセラー作品です。
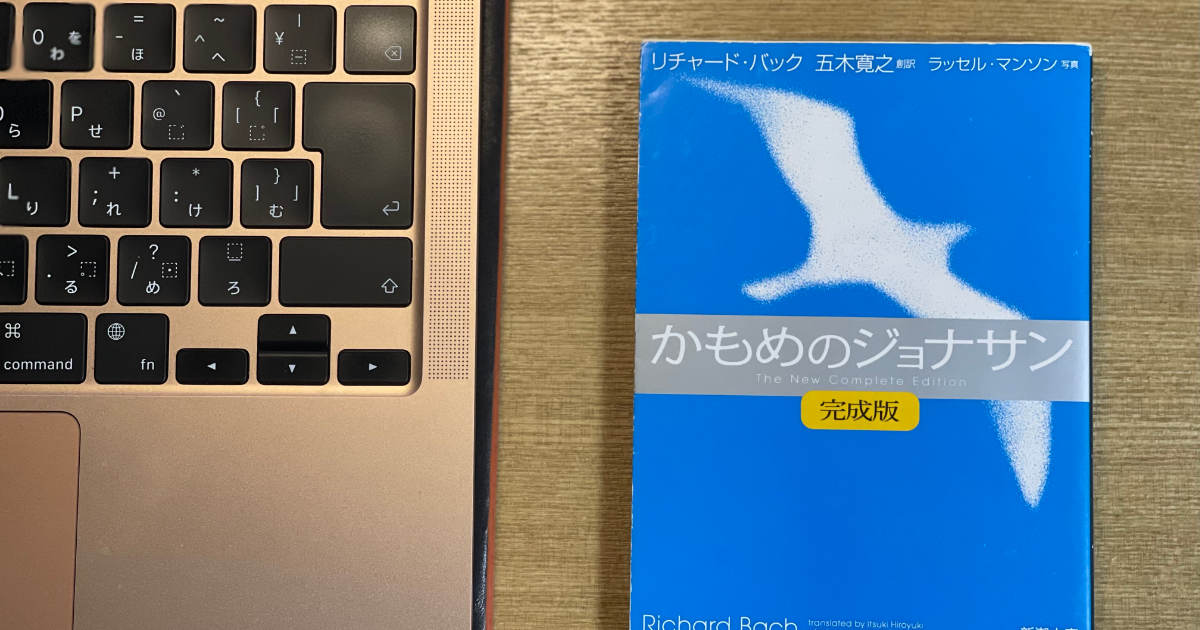
内容については詳しく書いた書評記事があるので割愛しますが、1時間程度で読める内容でありながら深く、自分自身定期的に読み返している1冊です。
Amazon ランキングで毎年4月になると上位に急上昇するのを見て初めて存在を知り、社会人2年目の頃に購入し通読しました。
「岩波文庫」と言えば海外の翻訳物や古典を中心に難解なものを幅広く取り扱っていることから、少し「手に取りにくい」と感じる方も多いかもしれません。
こちらの書籍も一言で言えば「古典的な指南書(古典の類)」なのですが、各指南が短文で構成されている(名言集のような作り)こともありとっつき易く、訳も併記されているので読みやすい作りとなっています。
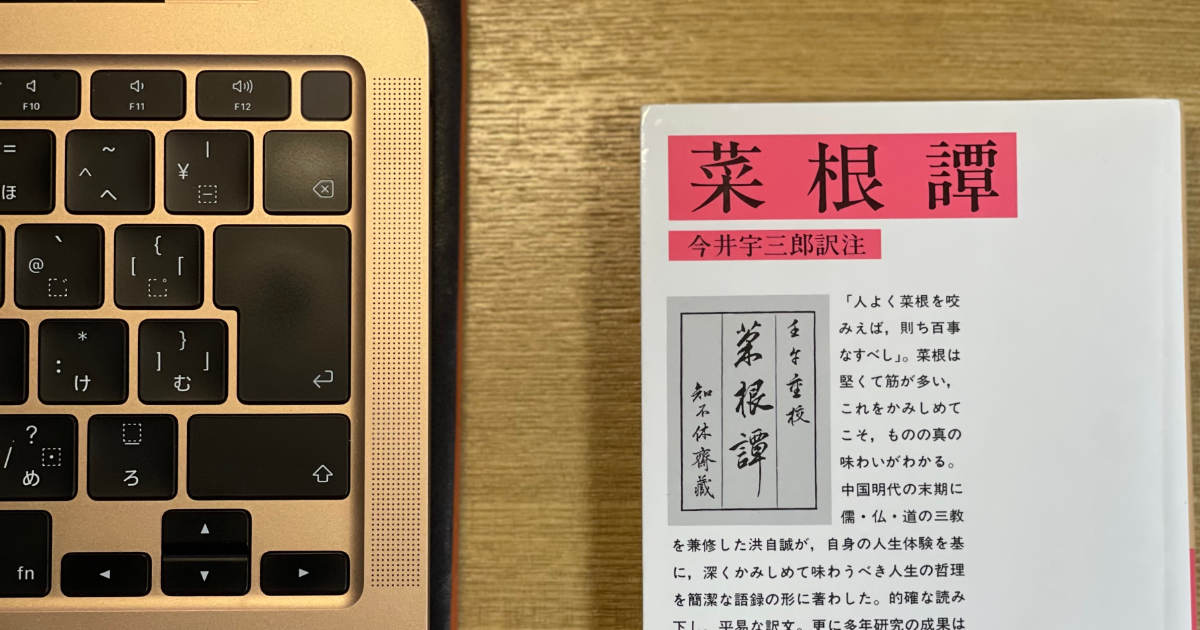
読み返すと「…あ、これは最近心掛けられていなかったけどおっしゃる通りだな」となるものも多く、社会人として初心を忘れそうな際に再読しています。
「何か一冊ビジネス書を」と聞かれれば、自分は迷わずこれを選びます。
スタジオジブリといえば宮崎駿や高畑勲をイメージする方も多いかもしれませんが、実態として「興行」に関しては鈴木氏がの尽力によるところが大きく、またそういった氏の仕事における脅威的な要領の良さがどのように成立しているのかについて、身近でサポートし続け、実際に見聞きした内容を石井氏がまとめたものが本書です。
著者である石井朋彦は、90年代の終わりにスタジオジブリに入社し、初めてアニメーション業界に携わるようになります。
氏はのちにProduction I.G4、株式会社クラフターの取締役などもつとめられています。
身近で鈴木敏夫の仕事を見続け学び続けたからこそ得られた知見が、惜しげもなく盛り込まれた一冊になっています。
読み進めていくと「今の日本では考えられないぐらい古風な指摘だな」と思える点も多々あるのですが、そういった細かい点も含めて、鈴木敏夫が如何に仕事に対して取り組んでいるのかを垣間見ることができる一冊となっています。
特に新人の頃、クライアントワークに苦戦した折に何度も読み返しました。
文学者であり思想家でもある内田樹が、一人のファンとして村上春樹作品について論じた文章をまとめたものが本作です。
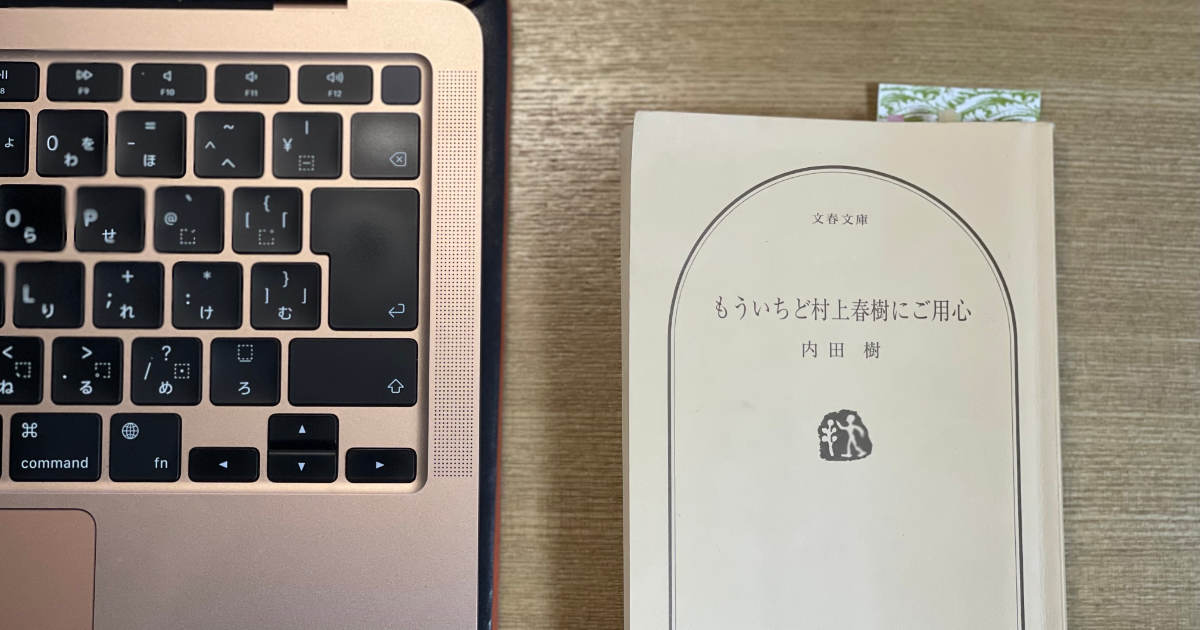
読むとわかりますが「評論」という形式を借りた、非常に気の利いた「ファンレター」でもあります。
しかしながらファン特有の卑しさは一切なく、「そもそも村上春樹の作品の魅力はですね…」と丁寧に内田氏が解説してくれる、そんな丁寧な1冊です。
自分は村上春樹作品については、代表作を一読している程度で、別段熱狂的なハルキストというわけではありません。
しかし、本作は正直、自分にとっては村上春樹作品以上に面白く、学生時代から何度も再読しています。
また誠に残念ながら Kindle 化されておらず、また文庫本はすでに絶版となってしまったため、自分は複数ストックし有事に備えています。
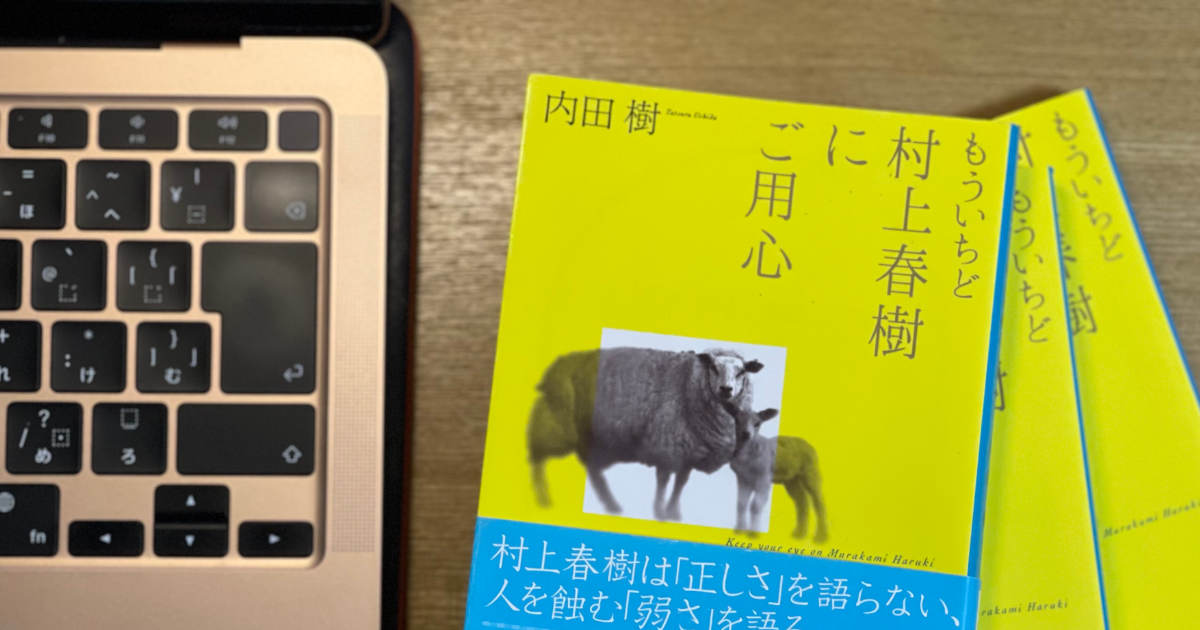
『村上春樹にご用心』という前作も存在し、それが加筆され刊行されたのが本書になります。こちらについては Kindle 版もありますので、ご安心ください。
ただ、個人的には情報も刊行時の最新作までカバーされており、更に読みやすい「もういちど村上春樹にご用心」の方がオススメです。
『ビジネスマンの父より息子への30通の手紙』は、社会人2年目の頃、当時の社長であった滝井さん@hidenoritakii に渡されて読んだ一冊です。
こちらも『かもめのジョナサン』同様にロングセラーのようで、作中冒頭、学生である息子と経営者の父親との手紙でやり取りから物語は始まり、父親のあとを息子が完全に継ぐまでに行われた30通の手紙でのやりとりがまとめられた実話をもとにした作品です。
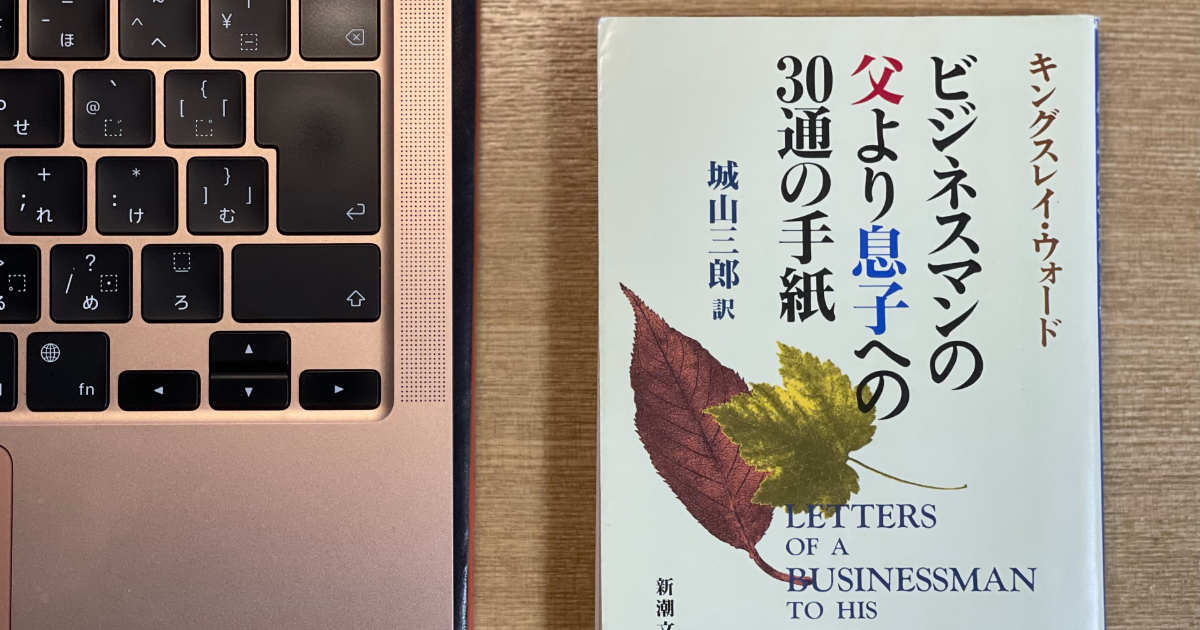
主人公が年齢を重ねる中で父親からもらったアドバイス(30通)をもとに構成されているため、年を重ねるごとに読み返すと、都度学びがある1冊です。
『エルメスの道』は、世界でも稀有なラグジュアリーブランド・HERMES の社史を紹介している竹宮氏による少女漫画5です。
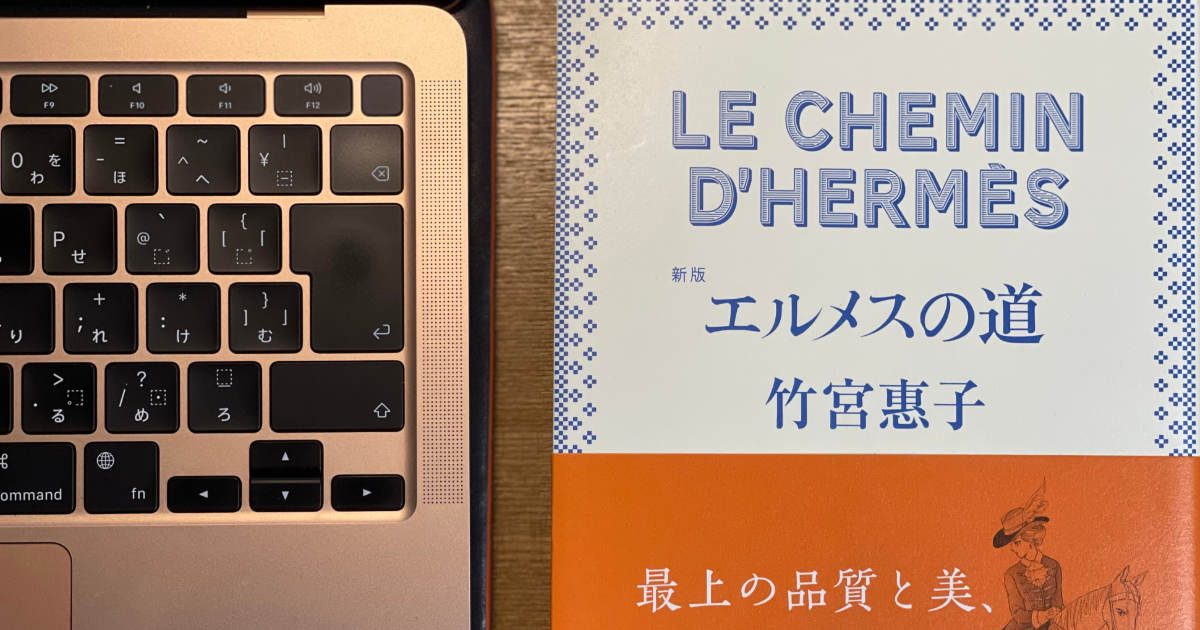
歴代の社主が如何に HERMES に対して尽力してきたのかが、本作を通読すると見えてきます。
例えば、一人の社主がその生涯を通じて1つのロングセラーを生み出しているサントリーなどと同じように、HERMES もまた、1つのロンセラー商品を生み出すのに1人の社主が丸々人生を賭けてトライし、その功績が次の代にそれが引き継がれ、それが脈々と何代も続いた結果、現在の地位を確立しているということが、通読するとよくわかるのです。
少女漫画と言う形式ということもあり、1時間程度で通読可能な上、1冊をしっかりと読み込むと「ブランディングが如何に一朝一夕でできるものではないものか」という事を、正しく理解する事ができるようになります。
初読は大学3年生の時でしたが、今でも、特に広告の仕事で壁にぶち当たり、「自分自身の真価を問われているのではないか?」と感じる際に再読する機会が多いのが『世論』です。
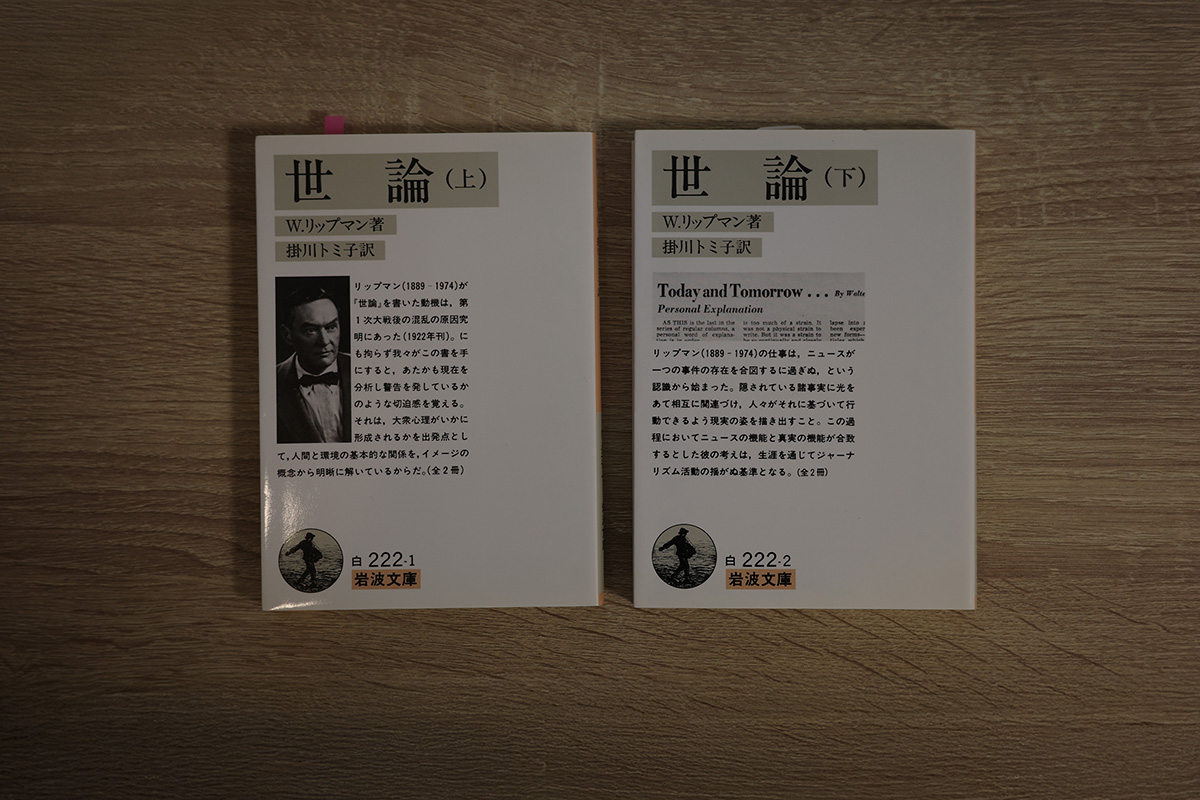
W.リップマンが描く痛切な「社会ってこんなものよ」「人間の情報処理能力ってこんなものよ」という事例の数々は、1920年代のアメリカにとどまらず、現代の日本でも通用する内容となっています。
本書最大の指摘は、「見てから定義しないで、定義してから見る」という点について論じている点にあるように思います。
下記記事のような予測を立てたり、またそれに類する記事を執筆する際にも、再び手に取ることも多い1冊です。
書評記事も不定期で書いています。
気になった方は拙ブログのタグ「書評」もご参照ください。
文責:川手遼一
- 過去にそういった依頼を受け、『なぜ通販で買うのですか』などを選書したことがあります。元記事はこちら。PPC-LOGでも書評記事を書き、過去にも紹介しています。 ↩︎
- アインランドおよびアインランドの著作に関しては、Donald J. Trump や Elon Musk 、Peter Andreas Thiel なども公の場で言及することがあるほか、外資系の方や投資関連の仕事をされている方と話をする際にも読了済みの方が多く、話題にしやすかったりします。ただ一方で「聖書に次いで読まれている」と帯に書かれていた時期がありますが、それほど読まれているという認識は自分自身ありません。 ↩︎
- 作中でたびたび主人公・ハワード・ロークは自分の才能を過信したり、社会的慣習に従うことを極端に嫌う描写が多々ありますが、自分はそういった点は反面教師に見立てて自分自身の中に取り込みました。 ↩︎
- ちなみに余談ですが、川手は個人的に石井氏がプロデューサーとして携わった「東野エデン」シリーズが大好きで、知った時に勝手に運命に近いものを感じました。 ↩︎
- 本書内にも記載ありますが、HERMESから出版社に対して「社史を漫画化したい」と連絡があり、著者に関しては「馬に乗れる人であること、馬を描ける人であること」というのがほぼ唯一の条件だったらしく、該当する竹宮氏に白羽の矢がたったそうです。 ↩︎