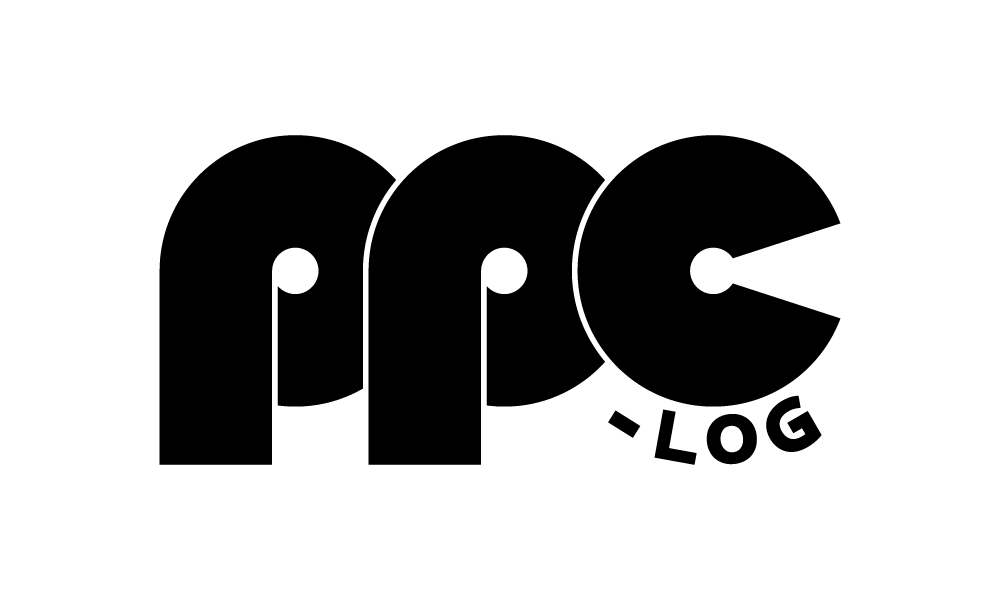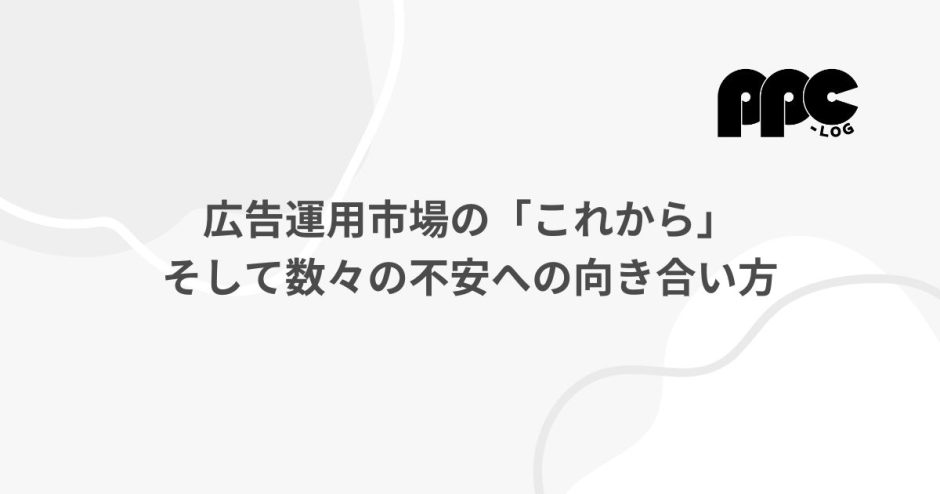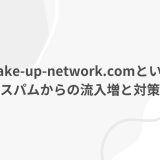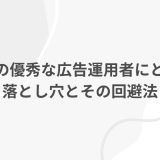当サイトは、Amazon.co.jp の商品を宣伝することにより、紹介料を獲得できる Amazon アソシエイト・プログラムの参加者です。
当記事に Amazon へのリンクが含まれている場合、それをクリックし買い物をすると、当サイト(および当サイト管理人)に対して一定の収益が発生します。
発生した収益の一部は、持続的なサイト維持のために使用されます。
ちなみに下記リンクをクリックし Amazon内で何かしら買い物をしていただくと、当サイト内で紹介した商品以外の購入でも収益は発生します。
もし「ブログの内容が役になった」「記事のおかげで助かった!」といった方は上記リンクをクリック頂き、Amazon内で買い物をしていただければ幸いです。
悩ましいのは、協力頂いた皆さんには持続的なサイト維持以外何の見返りもないということです。せめて皆さんから頂いた額を見て、ブログ読者の方への感謝の気持ちを忘れぬよう日々努めます。
先日下記ポストを見かけ、特にリスティング広告や運用型広告を中心に広告運用代行事業に従事しているジュニア層の方(業界経験の浅い方含む)が過度に不安を持つと良くないと思い、一筆したためました1。
以降の文章は社内チャットにてジュニアメンバー向けに投稿したものをアレンジ、修正したものとなります。
また島袋氏は SEO に関する案件についても言及していますが、本記事執筆者である川手は SEO に関しては素人であり、本記事では将来性などについては一切言及していません。
本記事は、あくまでも「リスティング広告を運用している一人のプレイヤー」として、現場で思い、感じているものを文章化したものであるとご理解ください。
目次
上記した通り、該当のポストでは以下事実が投稿されています。
MA市場で人気だったリスティング広告・SEO系のウェブマ案件のマルチプルは3倍いや2倍も難しい時代に突入したかも
引用元:島袋氏によるXでのポスト
要するに「(市場が)事業の将来性を低く評価している」という話をこのポストは伝えています2。
そしてまず、この情報は全面的に正しいと川手は認識しており、それを前提に話を広げていきます。
本記事は公開にあたり、発端となったポストを発した島袋さんから許可を得て公開しています。
詳細後述しますが、結論、「事業の将来性への評価」と「現場の実態」は多々異なっていることがあり、皆さんは明日以降の広告運用の仕事について、なんら過度に心配したり、「自分の仕事は将来性がないのではないか」と思い悩み、落ち込む必要はありません。
視点を「現場」に変えてみましょう。
皆さんは「最近、成果がすごく悪くなった」と感じますか?
少なくとも私には、その実感は皆無です。媒体担当者や、社外の様々な広告運用者の方と情報交換していても、AI などの台頭により「決定的に悪化した」という話は、寡聞にして聞いたことがありません3。
ただし、変化は起きています。
例えば、「低品質な記事を粗製濫造していた人」もっと言えば”仕事”ではなく”作業”だけしていた人。
こういった人が仕事や職を失うケースは、僕が目にする範囲でもすでに数件発生しており、今後も増えていくかもしれません。
ただこれは、AI 以前、もっと言えばインターネット以前の歴史を見ても定期的に起きている「最適化」にすぎません。
ダーウィンの『種の起源』をもとに独自に「適者生存」を論じたハーバート・スペンサーの主張に沿うのであれば、「最も強いものが生き残るのではなく、最も賢い者が生き残るのでもない。唯一生き残るのは、変化できる者」4です。
そういった最適化の波はこれまでにもたびたび訪れており、そういった変化も含め「不安定である」と見ている人も一定存在していることでしょう。
結論、株や会社の価値が「印象」や「イメージ」でも動くからです。
投資家が「AIの台頭で、検索エンジン領域は先行き不透明だ。リスクを避けよう」と判断すれば、MA市場での値付けや動きは鈍ります。
現場のパフォーマンスとは別のレイヤーで「領域全体のリスク」が懸念されている、ただそれだけのことです。
こうした情報に触れたとき、大切にしてほしい視点が3つあります。
Google 広告や Meta 広告は、クライアントの事業を成長させられる非常に優秀なツールです。
私たちが本質的な”仕事”さえしていれば、これらは安定してあらゆる情勢の変化に適用し、成果を出し続けてくれます。
そういった自分の「仕事道具」を信用しましょう。そして、仕事道具の手入れを日々怠るべきではありません。
「あの業界はオワコンらしい」
そういった外部の「世論」や「解釈」に振り回されてはいけません。
私たちが毎日触れているデータ、顧客との会話、商談の雰囲気。
そうした一次情報から物事を冷静に読み解き、判断する癖を、特にジュニアメンバーは身につけてください5。
またW.リップマンの言葉を引用するまでもなく、人は「見てから定義しないで、定義してから見る6」ため、それらの評価の蓄積が「世論」を形成しているのであれば、当然それらの蓄積には間違いも含まれており、それをもとに判断や決定を下そうとすると負荷がかかります。
逆に言えば、そういった論に耳さえ貸さなければ、不必要な情報に消耗することは少なくなるはずであり、本来やるべき「広告運用」という仕事にリソースを傾けることができるようになります。
前述の MA 市況環境を考えると、弊社前代表は変化が本格化する直前に「育てた子を外に出す7」と決断した判断そのものは評価せざるを得ませんし、その姿や姿勢、視野や視座から我々8はひとりの商人として学ぶべきことが山ほどあるように思います。
文責:川手 遼一
- 文中にも注書きを記載していますが、当該ポストを投稿した島袋氏はSEOを含むウェブマーケティングについて言及していますが、本記事執筆者である川手はSEOに関しては素人であり、本記事では将来性などについては一切言及していません。 ↩︎
- 川手は「マルチプルが下がる=事業の将来性への評価が下がっている」と認識しており、その上で論を展開しています。 ↩︎
- むしろ「AI Overviews(AIによる概要)が従来の自然検索流入や検索広告に及ぼしていると思われる影響に関する調査結果」という調査結果を自分が編集長を務めるキーマケLab で公開したところ、同業者間から「…あの調査結果はどうなの?」と建設的な議論を持ちかけていただくことが多々あったりしています。自分はそういった際に「調査結果はあくまで調査会社経由で調査対象者が考え(あるいは感じ)回答したものをまとめて公開しているにすぎず、必ずしも”事実”を数値で示しているわけではない」という前提のもと、ディベートさせていただくことが多いです。 ↩︎
- Google 検索で調べると「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である」という言葉は、チャールズ・ダーウィンの『種の起源』に書かれたものという主張が見受けられますが、自分が岩波文庫版『種の起源 上』『種の起源 下』やを通読した限りはそのような言葉はなく、どちらかといえば『種の起源』をもとに「適者生存」へと論を広げたハーバート・スペンサーの主張に基づく言説であり、それが社会一般に広まったというのが定説のようです(間違っていたらごめんね) ↩︎
- 上記ある通り、社内向けの文章をリライトし公開しているため、多少ジュニア向けのメッセージ性が強く、煩く受け止められてしまったようであれば申し訳ございません。ただ身につけることによって、メリットもあります。仕事に集中できるようになるほか、時には投資で成功することも起こり得ます。ただN=1ですので、まあ参考程度に。 ↩︎
- W.リップマンは『世論 上』にて、次のようにも述べています。「見てから定義しないで、定義してから見る。外界の、大きくて、盛んで、騒がしい混沌状態の中から、すでにわれわれの文化がわれわれのために定義してくれているものを拾い上げる。そしてこうして拾い上げたものを、われわれの文化によってステレオタイプ化されたかたちのままで知覚しがちである。」 ↩︎
- 引用元:社運をかけた提案の失注が転機に。代表滝井がグループジョインを決めるまでのストーリー/未踏市場への挑戦【前編】 ↩︎
- 本記事はもともと社内チャット向けに展開した文章を元に構成されており、我々=キーワードマーケティングの社員1人1人という意味です。 ↩︎